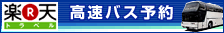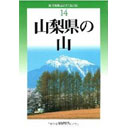|
|
 |
| 雲のかかる富士.農鳥岳山頂より. |
| 一日目:奈良田−大門沢小屋 |
 |
| 大門沢小屋から見えた夜明けの富士. |
 |
| 農鳥岳. |
 |
| 西農鳥岳. |
 |
|
| 大門沢の下降点を示す黄色い塔. |
 |
| 塩見岳. 西農鳥岳より. |
 |
| 東、中、前岳の三つからなる荒川三山.西農鳥岳より.東岳は完全に離れていて、コルの後ろには赤石岳が見えている.
右手には大沢岳の円錐も見える. |
|
奈良田行きのバスは、身延駅から出ている.東京発では、昼前のバスに乗るのが精一杯であり歩き始めるのは午後になってしまう.スタートが遅れる分、小屋まで
ややハードなスケジュールとなるが、奈良田から大門沢小屋はコースタイムで4時間40分、テント泊であれば日さえ暮れないうちに着けばよいので問題はないだろう.
甲府駅から身延線に乗り身延駅で降りた.駅前を出発した奈良田行きのバスは、国道52号線を進んで早川筋に入った.
早川源流の野呂川は、北岳の西北に発し
北岳西に発し、甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳の間を下る北沢を合わせて北岳を半周した後、間ノ岳、農鳥岳と続く南アルプスの東側山稜と、夜叉神峠から南に続く山稜にはさまれた
狭い峡谷を南下、流れが七面山や身延山に行く手をさえぎられたところで、東に向きを変え富士川に合流している.
広々とした河原をみせていた早川も、雨畑あたりから山峡の流れとなった.狭い峡谷の底に道が続き、両岸の崖はおそろしく高い.西側の壁を作っているのはアルプスの高峰で
あり、海抜で1000メートルに満たない峡底まで一気に切れ落ち、やや薄暗く感じるのも、決して気のせいだけなのではなく、陽はこの壁に遮ぎられているからかもしれない.トンネルを抜
けた橋のところの停留所で登山者がひとり降りていった.ここが伝付峠の入口だ.乗客は私のみとなりバスはさらに山峡を進む.やや広いところに出て、いよいよ奈良田集落である.
バスを降りて早速歩き始める.北岳の登山口もある広河原まで谷底に続いている道路は南アルプス街道、ここから歩いて30分ほど北に、大門沢登山口、広河内がある.
銀色に塗られた奈良田橋で対岸に渡り、進むと東京電力の発電所があり、早川水系発電管理事務所と表示されている.流れ込んでいるのが広河内沢で、沢沿いの車道を15
分ほど登っていくと、登山者名簿が置かれていてベンチもあるので、ここに腰掛け遅い昼食を食べていくことにした.
再び歩き始め10分ほど進むと吊橋で右岸に渡るようになっている.この先にはすぐ2つめの吊橋で左岸にもどる.登っていくと取水堰にでた.ここも吊橋を渡り右岸を進むようになる.
木橋で支沢を越えると、北西に向けて進むようになり、流れ込むやや大きな沢、大古森の沢を越える.沢を渡れば細い道幅の急登で、一段高くなったところに出る.地形図の等高
線間隔が広くなっているあたりで緩い勾配の道を歩いていくと、小さな支尾根を越える.
やや下りになった道を進むと沢づたいとなり、木橋を左岸に渡るようになっている.沢の上流に小屋
も見えてくるのだが、見た感じほどにすぐには着かない.右岸に渡ると大門沢小屋につき、本日の行程は終った. |
| 二日目:大門沢小屋−山頂ー奈良田 |
 |
| 農鳥岳山頂 |
 |
| 山頂のはっきりしない西農鳥岳のピーク.背後に見えているのは、間ノ岳. |
 |
| 富士. |
 |
| 間ノ岳.下に農鳥小屋が見えている. |
 |
| ガスが切れて現れた北岳.南から見る北岳は、委細で美しい. |
 |
鳳凰三山.山頂部がいずれも白い三山.地蔵岳はオベリスクが突き出ていて特定しやすい.農鳥岳より. 鳳凰三山 鳳凰三山 |
|
大門沢小屋から農鳥岳山頂までは、コースタイム4時間40分.できれば西農鳥岳まで行きたいから、
時間はできるだけほしい.初めての道だけに、暗闇のスタートは少し不安が残るが、今日は4時スタート.懐中電灯で踏み跡を追いながら進む.あたりがやっと明るくなったころ、道は沢沿いとなって、
やがて沢床に降りてしまった.沢底をしばらく登っていくと、いよいよ急坂が始まった.時刻は5時6分で高度計は2200メートルを指していた.ここまで1時間で500メートルほど登ったことになる.
稜線は2850メートルあたり、650メートルの登りが今日の勝負どころで、コースタイムからは3時間を要する計算だ.沢を詰めていくだけに登りは相当きつくなることだろう.覚悟はしていたけれ
ど、登り始めると急坂の連続にうんざりしてくる.陽が出てきて喜んだのもつかの間、今度は小雨までぱらついてきたから、思い切って十分な休憩をとってから、再び歩きはじめた.まわりはハイマツに
変わった.そろそろ稜線かと期待して進むがなかなかたどり着かない.まだ稜線までありそうなので、小さなピークの裏を越えたところで再び15分の休憩をとることにした.
稜線に登りつくと、農鳥岳から南下し広河内岳まで続いている縦走路に出た.黄色の鉄製やぐらに大門沢と書かれている.残念ながら天候もまだ落ち着かない.視界が開けてきたと喜んだや
さきにまた真っ白に変わってしまった.縦走路に出てしまえば、すぐにでも山頂のような気がしていたが、ここからも意外と長い.30分ほど進んだピークのところで空は晴れに向かい始めた.今度は期待
してもよさそうだ.山頂もすぐ先にあってもういくらも時間はかからない.
もう5分も待てば視界が開けそうだ.下山してくる団体がすれ違った.農鳥小屋を出てきたのだろうか、足早に降りていくが、昨日も雨天で視界はなかっただろうから、せめてここで展望を楽しん
でいけば良いものをと思う.
時刻は7時56分.4時間弱で山頂に達した.下山のコースタイムは、小屋までが3時間、そこから先奈良田まで3時間40分要するから、合わせて6時間40分.登りで40分節約できているから、
下りもいくぶん急げば、奈良田まで6時間は難しくなさそうだ.少し忙しいが、午後4時代にあるバスに乗るには10時ころ山頂を発てばよいことになる.
農鳥岳は2つのピークがある.間ノ岳側からみたとき、手前の小さなごつごつしているピークは西農鳥岳であり標高3051メートル、農鳥岳の三角点3026メートルより高い.西農鳥岳までは1時間も
あれば往復できそうだから、まずは30分休むことにした.
富士山の山頂部は先ほどから見えていたけれど、全体がはっきりわかるようになってきた.今年は富士登山も予定しているけど、今日のような雲がかかった山頂、もしそこにいたら、吹き上がる風
に冷やされて結構きつい思いをすることだろう.
西農鳥岳との間には、コルがあって山頂西側を一端下り、登りなおすと西農鳥岳に着く.すぐ隣にある間ノ岳はもちろん、南には、小さな三角形を載せた特徴ですぐわかる塩見岳や、さらに、荒川三
山と赤石岳も見えていた.間ノ岳の先にあるはずの北岳は見えていなかった.山頂で30分ほど過ごしてから、東農鳥岳に戻る.
時刻は10時、そろそろ下りに入りたいが、北岳も晴れてきそうな気配がするので待ってみることにしたのであるが、ガスが薄れてもなかなかその姿を見せてくれない.20分ほどまって、
あきらめかけたとき、終にあのとがった北岳の全貌があらわれた.しかし、それもほんの一瞬、また登ってきたガスに隠れてしまった.すでに時間に余裕はない.あきらめ下りに入った.
|
| 西農鳥岳 |
 |
熊ノ平小屋からみた西農鳥岳
 蝙蝠尾根 蝙蝠尾根 |
 |
三峰岳からみた農鳥岳
 間ノ岳 間ノ岳 |
 |
| 山中湖の東にある明神山よりみた南アルプスの峰々.右の3つが白峰三山 |
|
|
| 略図 |
|