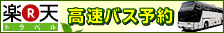青梅街道を渡すコンクリートアーチ橋、氷川大橋の上に立ち、深い川底を見下ろし、奥多摩町の山深さを
再度確認させられたことがあった.
休日、登山客で賑わうJR奥多摩駅、東京駅までうまく乗り継げれば2時間ほどしかかからない. そんな時間感覚も手伝ってか、私の頭の中では山間いう印象が薄くなりつつあったのであるが、この橋に立 てば、四方は山々の急斜面に囲まれ、わずかな平地に家々寄り添う、山間の僻村であった氷川の姿を垣間見 れたような気がした.
氷川大橋の元で、雲取山に発する 日原川は、遠く山梨県の笠取山水干に発する多摩川に流れ込んでいる.2つの流れを分けている東西に延びる 長い尾根、石尾根の突端が終に川底に達するのがこの氷川である.
関東平野から登ってきているとはいえ、奥多摩駅は、まだ海抜400mに達してはいない.都の最高地点である 雲取山の山頂2018mまでまだ1600メートルを残している.この石尾根を伝って雲取山に達するルートは、 次々に枝尾根からの登山道を合わせていき、9時間ほどで雲取山に到達するから、早朝出発、一日精一杯登って ちょうどの時間だ.
長丁場ゆえに、登り終えればその達成感も加わり、都の最高峰を制覇した喜びが感じられるかもしれない. 最高峰という言葉にこだわるのなら、もっとも比高の大きいこのルートを選ぶべきかもしれない.ただ、鷹ノ巣 山あたりまでは、このルートをあえて伝う魅力には乏しい.首都という木材の大消費地に隣接していた奥多摩と いう地は、林業も人々の暮らしを支えてきた重要な産業であるから、植林は稜線にまで達していて、薄暗い植林 の中を縫う歩道を登ることになる.
植林の中を延々と登らなければならないことに抵抗を感じる私は、このルートをあえて選ぶ気にはならな かった.今回は、石尾根の主要ピークである鷹ノ巣山へ北東の稲村岩尾根からアプローチすることに決めた. この尾根の日原川に達する末端には稲村岩という円錐形の見事な石灰岩搭が立ち、それゆえにこの尾根の名がある.
この尾根を登った経験がない私にとって、急坂続きの下りに好まれて使われているルートは、登り始めて 早速疲弊してしまわないか気がかりなものだったが、10月後半ともなれば、少しくらいの急登であっても汗だ くになって登ることもないだろうし、この時期、日原から見あげるこの尾根は、まだらに色づき、落葉樹の下を 登っていくことが予想できるから、多少勾配のきつさがあっても、気はまぎれるはずである.
そして、この前半部を少しがんばって終えれば、鷹ノ巣山から先の縦走路は、ほとんど勾配もなく、のんび り歩けば時間にして3時間、小雲取山手前にある雲取奥多摩小屋に難なく着くはずだ.昼までに鷹ノ巣山に登り、 展望の良い山頂でゆっくり昼食を取ってから、歩き出せば日没までには十分辿りつく計算になる.
ここで一泊、翌日山頂までは比高200mを残すのみで1時間を要するだけだ.帰路は小雲取山から野陣尾根を 日原川に下る富田新道を使い、出発点東日原バス停に戻ることにした.
この富田新道も急勾配であるけれども、ここはブナやミズナラの林の中の利用者も少ない静かな歩道で、時間的 には短くなるから帰路としては良いルートに思える.ただ、日原川林道に出てからの車道歩きは長いが、それでも東日 原バス停まで戻っても4時間ほどの日程で、早朝にテントを撤収して出発しなくてもよい.
この計画でいけば、往路早朝の電車にあわせて家を出ていかなければならない必要もないし、帰路も昼過ぎのバ スで戻れそうだから、週末1泊の山行予定としてはちょうど良い.「奥多摩の山は気楽に登るべき」という私の基準は 今回も適用され、出来栄えのよいプランが完成した.
休日、登山客で賑わうJR奥多摩駅、東京駅までうまく乗り継げれば2時間ほどしかかからない. そんな時間感覚も手伝ってか、私の頭の中では山間いう印象が薄くなりつつあったのであるが、この橋に立 てば、四方は山々の急斜面に囲まれ、わずかな平地に家々寄り添う、山間の僻村であった氷川の姿を垣間見 れたような気がした.
氷川大橋の元で、雲取山に発する 日原川は、遠く山梨県の笠取山水干に発する多摩川に流れ込んでいる.2つの流れを分けている東西に延びる 長い尾根、石尾根の突端が終に川底に達するのがこの氷川である.
関東平野から登ってきているとはいえ、奥多摩駅は、まだ海抜400mに達してはいない.都の最高地点である 雲取山の山頂2018mまでまだ1600メートルを残している.この石尾根を伝って雲取山に達するルートは、 次々に枝尾根からの登山道を合わせていき、9時間ほどで雲取山に到達するから、早朝出発、一日精一杯登って ちょうどの時間だ.
長丁場ゆえに、登り終えればその達成感も加わり、都の最高峰を制覇した喜びが感じられるかもしれない. 最高峰という言葉にこだわるのなら、もっとも比高の大きいこのルートを選ぶべきかもしれない.ただ、鷹ノ巣 山あたりまでは、このルートをあえて伝う魅力には乏しい.首都という木材の大消費地に隣接していた奥多摩と いう地は、林業も人々の暮らしを支えてきた重要な産業であるから、植林は稜線にまで達していて、薄暗い植林 の中を縫う歩道を登ることになる.
植林の中を延々と登らなければならないことに抵抗を感じる私は、このルートをあえて選ぶ気にはならな かった.今回は、石尾根の主要ピークである鷹ノ巣山へ北東の稲村岩尾根からアプローチすることに決めた. この尾根の日原川に達する末端には稲村岩という円錐形の見事な石灰岩搭が立ち、それゆえにこの尾根の名がある.
この尾根を登った経験がない私にとって、急坂続きの下りに好まれて使われているルートは、登り始めて 早速疲弊してしまわないか気がかりなものだったが、10月後半ともなれば、少しくらいの急登であっても汗だ くになって登ることもないだろうし、この時期、日原から見あげるこの尾根は、まだらに色づき、落葉樹の下を 登っていくことが予想できるから、多少勾配のきつさがあっても、気はまぎれるはずである.
そして、この前半部を少しがんばって終えれば、鷹ノ巣山から先の縦走路は、ほとんど勾配もなく、のんび り歩けば時間にして3時間、小雲取山手前にある雲取奥多摩小屋に難なく着くはずだ.昼までに鷹ノ巣山に登り、 展望の良い山頂でゆっくり昼食を取ってから、歩き出せば日没までには十分辿りつく計算になる.
ここで一泊、翌日山頂までは比高200mを残すのみで1時間を要するだけだ.帰路は小雲取山から野陣尾根を 日原川に下る富田新道を使い、出発点東日原バス停に戻ることにした.
この富田新道も急勾配であるけれども、ここはブナやミズナラの林の中の利用者も少ない静かな歩道で、時間的 には短くなるから帰路としては良いルートに思える.ただ、日原川林道に出てからの車道歩きは長いが、それでも東日 原バス停まで戻っても4時間ほどの日程で、早朝にテントを撤収して出発しなくてもよい.
この計画でいけば、往路早朝の電車にあわせて家を出ていかなければならない必要もないし、帰路も昼過ぎのバ スで戻れそうだから、週末1泊の山行予定としてはちょうど良い.「奥多摩の山は気楽に登るべき」という私の基準は 今回も適用され、出来栄えのよいプランが完成した.
|
|||||||
|
|
|||||||||
| 稲村岩 | |||||||||
| 遅い歩き出しだった.バスを降り、中日原まで歩く.稲村岩と鷹ノ巣山の登山道は日原川びの谷に向けた急な下りで始まる.河川の高さまで降りると、
巳の戸橋で対岸にわたる.登山道はじきに、巳ノ戸沢におり沢床を歩いていくことになった.朽ちた橋がかかり、巳ノ戸歩道が分岐しているが、立ち入り禁止になっていた.この巳ノ戸歩道は北側の八丁山に向かって登り、山頂西側で避難小屋も建っている巳ノ戸のくびれに登れるようになっていたようだ.
稲村岩には、沢の右岸を一気に尾根の背に這い上がる.
スイッチバックしながら尾根の背に出たところは、稲村岩の分岐で時間はどうにか間に合いそうだから、ついでに立ち寄っていくことにした. 後半は岩を攀じ登る感じでピークに達する.日原を訪れるたびに、何度も見上げてきた山脚に立つ円錐形の岩、岩頭に立つのは今日が始め てだ.意外だったのは木々に取り囲まれていて、それらに邪魔されて180度の視界があるわけではないことである. 東には、急な斜面に立ち並ぶ日原の山里、その背後には無機質な灰色の山肌を露出してている.道路の日原トンネルの上にある砕石場で、奥多摩駅 の奥にある工場に石灰岩を供給していた.今立っているここも、観光名所の鍾乳洞も日原と石灰岩のつながりは強い.戦時中でさえ奥多摩まで線路が延長され たのも、セメント需要を支えるという目的があったからであろう.奥多摩は石灰岩に支えられている. 奥多摩駅のある氷川の街をその下流から分断している本仁田山の山姿も見える.肩幅の広いこの山の左から、デコボコに上がっていく稜線が続いている. 川苔山の舟井戸のコルに向かう鋸尾根のあたりだ.歩いたときには急な登り降りが続いていたのであるが、遠方から見てみると こう名づけられた理由がよりいっそうわかる. 反対側を向くと、西に尾根がまっすぐ登っている.まだ少し時期は早いようで、ちらほら紅葉の混じっている程度であった. その南側の窪みが鷹ノ巣沢で、北側は先ほど登ってきた巳ノ戸沢が突き上げている. ここからは、山頂はまだ見えていないようだ.まずはこの尾根を登らなくてはならない.雲取山への日程は今始まったばかりである. 登山道に戻る途中で北側の燕岩のあたりがよく見えていることに気づいた.針のような尖塔、梵天岩がその前に立つ. 実際にこの岩の下に立ったときには太く細いので針のようには見えなかったのであるが、遠くから見るとその細さが際立っている. |
|||||||||
 |
 |
||||||||
| 右:見事な円錐形、中日原と深い谷を挟んで立つ稲村岩.登山道入口はここに始まる. 左:稲村岩は石灰岩.岩頭に立ってみるとは、木々に囲まれて想像していたほどの視界はなかった. 頂上のこの小さな岩に上がると少しだけ展望は広くなった. |
|||||||||
 |
 |
||||||||
| 左:稲村岩の上からは奥多摩入口部の山々の展望が良い.右側の台形のピークは本仁田山.そこからギザギザになって、川乗山に稜線は登っていく.この部分は鋸尾根と
名づけられているのが、ここから見て初めて理解できた.石灰岩砕石場の削り取られた斜面の手前には日原集落の家々が見えていた. 右:稲村岩上から紅葉の混ざった尾根を見上げる.鷹ノ巣沢(左)と巳の戸沢(右)に挟まれて、鷹ノ巣山に向かい突き上げているのが稲村尾根. |
|||||||||
| 稲村岩の登り口から北の小川谷を見る.篭岩が見え、その前に燕岩の白い尖塔が確認できる. |  |
||||||||
| ヒルメシクイのタワ | |||||||||
| 登山道に戻れば、山腹の単調な登りが続いた.時に緩くなったりして、せいぜいこの勾配の変化を楽しむくらいであろう.
美しく紅葉した木の下では、晴れた渡った空の青とのコントラストを楽しむために、木々を見上げて立ち止まる.
ブナやミズナラの大木が増えてきた.北方には天祖山が見えてきた.考えてみれば、この山とは小川谷を挟んで対峙して
いるのである.そして、ヒルメシクイのタワに出る.
そもそも、奥多摩の鷹ノ巣山という山に対して私が初めて興味をもったのも、その名づけの素朴さがあまりにも 印象的であったこの地名からであった.奥多摩ではタワという地名がよく出てくる.鞍部であるから、せりあがった 沢に下りれば水も得やすい.山仕事に来て弁当のために茶を沸かした場所であったのだろうか. 前方の樹間には、まだだいぶ標高差を残したまま山頂らしきピークが望める.あと30分といったところか. 距離にしてみれば、まだわずかにしか終えていないのであるが、鷹ノ巣山から先のピークは巻いてしまう予定な ので、登りは七ツ石山と小屋に達する終盤だけだ.今日は、ここが最後のがんばりどころなのだ. ところが、この登りは意外にも容易に終わり、20分ほどで山頂に出てしまったのである. |
|||||||||
 |
鷹ノ巣山の肩の部分がヒルメシクイのタワ. | ||||||||
| 鷹ノ巣山 山頂 | |||||||||
|
|||||||||
 |
峰谷から登山道がついている浅間尾根.この前、この鷹ノ巣山にこの尾根伝いに登った時はまだ新緑前だった. 早いもので、それからもう半年が過ぎ去っていた. | ||||||||
 |
東側、奥多摩入口部の最もわかりやすい峰は大岳山、そのとなりは御前山. | ||||||||
| 石尾根 鷹ノ巣山から日陰名栗の峰 | |||||||||
 |
山頂から避難小屋に向けては防火帯の急な下りになる. | ||||||||
 |
鷹ノ巣山山頂を西に下り始めると右手に雲取山が見えた. | ||||||||
 |
日陰名栗ノ峰. | ||||||||
 |
巻き道を使うと日陰名栗ノ峰は南側を巻いて進む. | ||||||||
| 石尾根 高丸山から七ツ石山 | |||||||||
 |
高丸山.日陰名栗の鞍部からみる. | ||||||||
 |
高丸山.日陰名栗の峰鞍部に立つ指導標. | ||||||||
|
|||||||||
 |
赤指尾根. | ||||||||
 |
鴨沢から登る尾根. | ||||||||
| 七ツ石山 | |||||||||
|
|||||||||
 ルート <1/25000地形図> 奥多摩湖、武蔵日原、雲取山 |
|||||||||
|
|
|||||
| 山頂へ | |||||
|
|||||
 |
雲取山、2018mの山頂.三角点は避難小屋の北側の一画にある.西に奥秩父の山々が見えている.大岳山など奥多摩入口部の山や、富士を始めとする 南側の山々は避難小屋前の方が展望が利く.山頂部から見える山々ついてはこちらをご覧ください. | ||||
|
|||||
 |
飛竜山 | ||||
 |
特徴のある大岳山と、そのとなりには御前山. | ||||
 |
小雲取山に続く尾根を避難小屋手前から写す.背後に七つ石山が見えている. | ||||
 |
雲取山から小雲取山間の尾根から富士を望む. | ||||
| 野陣尾根 [富田新道] | |||||
 |
小雲取山から野陣尾根を下り始める.歩き始めはカラマツ林の中を進む. | ||||
 |
小雲取から野陣の頭までは、比較的平坦な道が続くが、 その後、急坂に変わる.このあたりは、ミズナラやブナの大木に囲まれた紅葉が美しい. | ||||
 |
唐松谷側にでると急斜面をスイッチバックの繰り返しが続く. | ||||
 |
ブナ坂から下ってくる唐松林道が合流し、続けて急坂を下れば唐松谷に出た. | ||||
 |
唐松沢は滝となって注ぎこみその上を 吊橋で渡る.この吊橋が架けられているのは大雲取沢の方だが、唐松橋と呼ばれているようだ. | ||||
| |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2001-2010 (C) Masashi Koizumi. All Rights Reserved.