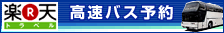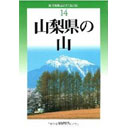地形図 このコースの範囲であれば、二万五千分の一地形図では、千丈ヶ岳、鳳凰山の2枚でカバーする.池山御池小屋経由
で登るのなら、夜叉神峠、間ノ岳、農鳥岳の縦走をもくろむのであれば、これに加えて、間ノ岳が必要になる.
![]() 国土地理院地図閲覧サービス
国土地理院地図閲覧サービス
登山用地図で、私の愛用しているのは、「 ヤマケイ登山地図帳4 北岳・甲斐駒・仙丈−南アルプス北部」と、ゼンリンの「登山ハイキング7 北岳甲斐駒」の2種であるが入手できない.
- 北岳・甲斐駒南アルプス 昭文社 2008年版
- Jマップ北岳・甲斐駒ヶ岳

- 仙丈ヶ岳を、
 Yahoo地図情報でみる.
Yahoo地図情報でみる.
藪沢ルートへ下った2002年の山行で実際にかかった時間を 記してあります.途中何回か取った休憩時間は含まれていません.
- 第1日
- 甲府駅
- 2時間半(バス)
- 広河原
- 30分(市営バス)
- 北沢峠
- 5分
- 北沢長衛荘
- 第2日
- 北沢峠
- 40分
- 三合目
- 30分
- 大滝頭
- 60分
- 小仙丈
- 45分
- 山頂
- 35分
- 小仙丈
- 25分
- 大滝頭
- 20分
- 藪沢小屋
- 10分
- 藪沢渡渉
- 35分
- 大滝展望台分岐
- 25分
- 大平小屋
- 10分
- 北沢峠
- 25分(市営バス)
- 広河原
- 2時間半(バス)
- 甲府駅
北沢峠からの小仙丈尾根ルートのほかに、私が下山に使用した藪沢コースがある.大平山荘から樹林中を登り、藪沢に出ると甲斐駒を背に沢の左岸につけられたルートを辿る. 馬ノ背ヒュッテを経由仙丈小屋から藪沢カール西側の壁をのぼり山頂に達することができる. ほかには、馬ノ背の尾根を行く丹渓新道コース、両股小屋から野呂川越に登り、大仙丈ケ岳を経由する仙塩尾根を伝うコースもある.
- 駒仙小屋

小仙丈岳へ
この仙丈ヶ岳に始まり、間ノ岳から西に伸び野呂川源流右俣沢と大井川源流を 分水している尾根をあわせ塩見岳まで達する長い尾根は仙塩尾根と呼ばれている. この尾根は、さらに南に続いていて赤石岳など南アルプス南部の峰々をも連ね、山脈 西側を貫く主脈である.
その北端の山、仙丈ヶ岳はその稜線に深い切りこみをいれている、野呂川筋の2つの 支谷、小仙丈沢、大仙丈沢によって3つの頂をみせる.これら東側2つの谷と戸台川に 流れ込む北側藪沢は、圏谷となっており、山頂部を囲む3つの圏谷がこの山の特徴であ ることに異論はないだろう.それらの間に細く残っている稜線の最高点がこの仙丈ヶ岳 山頂で3033mの標高がある.
南アルプス北部の山は、南アルプス林道を運行するバスが利用できることから、 南アルプスを代表する山々となっていて訪れる人は多い.
甲斐駒と並びこの仙丈ヶ岳は、登り口となる北沢峠までバスでアプローチでき、早朝 発日帰りも可能な山、もっとも手軽に登れる南アルプス3000メートル峰である.
北沢峠バス停を出発、樹林中の登りにしばらく苦しめられれば、見晴らしの良いハイ マツの登りに変わり小仙丈ヶ岳と名のついたピークに立つことになる.このピークを後 に、小仙丈カールに沿って緩い登り坂を進めば山頂部に達する.

三合めを越えると北岳側の展望がときおり現れる.休息所、樹間に北岳が見えてきた.

大滝の頭から藪沢に向かうルートが分かれる. しばらく登ると、樹林帯を終え小仙丈ヶ岳へ向けての登りになった.ここから先、山頂までは、 この山の魅力ともなっている展望のよい歩道が続く.

馬の背. 藪沢をはさみ向かいは馬ノ背の稜線. 木々の中に馬ノ背ヒュッテが見えている.

白峰三山の第2峰、間ノ岳.野呂川源流、右俣沢がつきあげていて、その右手に小高く 出っ張っているのが、仙丈ケ岳から塩見岳に続いている仙塩尾根上にある三峰岳のピーク.
仙丈ヶ岳山頂へ
小仙丈ヶ岳から先、カール上端を左縁とする緩やかな稜線を進むことになる. 左手に現れる小さなピークをやり過ごすと、この山の最高点.
仙丈小屋のある藪沢方面と大仙丈方面の分岐が現れ、そのすぐ南が狭い山頂 である.コースタイムで北沢峠から4時間、朝のバスで来るとちょうどお昼前に着く. 昼食を取る登山者でこみ合っていたが、どうにか場所を見つけて腰を下ろせば、まず は、北側、甲斐駒の白い花崗岩が作る異様な山頂部の姿に圧倒される.
こちらからみる甲斐駒は、摩利支天のみか、荒々しく刻まれた山頂部さえもいくらか 丸みを帯びているように見える.

仙丈ケ岳山頂部. 仙丈小屋の建っている藪沢カールと小仙丈沢カールにはさまれた 稜線にピークが並んでいる.仙丈ヶ岳の山頂は、右にあるピーク上で、ただそこが最高点を示しているのに過ぎない感じだ.

富士山は東南東の方角にあり、北岳の稜線越しに見えている.

もっとも目を奪われるのは、正面に位置する甲斐駒ヶ岳の姿であろう.

大仙丈ヶ岳方面の分岐があり、そのすぐ上が山頂.

地形図の表記は3032.6m、四捨五入して3033m.

藪沢左手の尾根は馬ノ背.稜線の直下に茶色赤屋根の馬ノ背ヒュッテがあるのがわかる.
下山
基本的に、バスの利用できる北沢峠に戻ることになるから、登路をそのまま戻る人 も多いようだが、せっかくなら違うルートを下山したい.藪沢側へ下ることにした.山頂を見ながらどんどん下っていくと 藪沢カールの底に建つ仙丈小屋の前に出る.
早いがここで一休み、先ほどまでいた山頂部の眺望を楽しんでから、馬ノ背ヒュッテ側に進む.ややのぼり気味になった ところに分岐が現れ、そのまままっすぐいけば馬ノ背を進む丹渓新道というルートで林道に出ることも可能だが、北沢峠へ もどるには、かなりの林道歩きが必要になる.
馬ノ背ヒュッテから大滝の頭にもどるルートを取るのが一般的だろう.下ればすぐ、馬ノ背ヒュッテに出る. 大滝の頭へ向かうルートを進むと藪沢に接する.ここを左に折れ沢沿いに下っていくのが藪沢ルートート、以前、 こちらに下ったこともある.
藪沢を越えれば、藪沢小屋が現れ、大滝の頭の分岐に出ることができる.ここからは、往路を単調な樹林 中の下りを繰り返し、北沢峠に下ることになる.
藪沢ルートにはいれば、ルート前半は沢に沿って下っていき、藪沢大滝の手前から樹林中の 下り道となる.途中この大滝への分岐も現れるが、残念ながら荒廃で立ち入り禁止になっていた. さらに、樹林を下っていくと、大平山荘のすぐ裏手に出て、わずかではあるが林道をたどれば北沢峠に出ることができる.

藪沢に沿って下るこのコースは、支谷を渡渉しながら大平小屋に向かう.7月でも沢筋には 残雪が見られた.

藪沢沿いからは、ちょうど正面に甲斐駒ケ岳が見えていた.